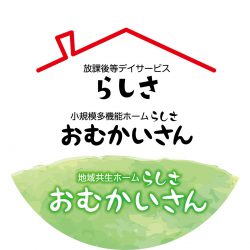法人(事業所)理念
【高齢者との共生『思いやりの心』を育て『成功体験』の積み重ねで『社会を生き抜く力』を磨きます】
おじいちゃん、おばあちゃん達と過ごす時間は、核家族化の進む現代では大変貴重と言えます。
小さい頃からお年寄りと関わった経験はこれからさらに進む超高齢社会においてとても重要です。
支援方針
【ひとりひとりの自分らしさを大切に「共」に「生」きる】
“体験”することが必要と考えています。
社会生活では多くの人と出会い、様々な経験をします。
らしさでは共生が作り出す「社会」の中で人と人が関わることこそ学びの機会であると考えます。
そこで積み重ねた成功体験はやがて自信に変わり、”社会を生き抜く力”に育つと信じています。
営業時間
9時から18時まで
送迎実施の有無
あり・なし
支援内容
本人支援
健康・生活
心身共に健康で安全な生活ができるように健康状態の把握や生活リズムの安定を目指します。
ひとりひとりのペースを大事にしながら「得意な事をのばす」「苦手な事でもチャレンジして出来るようになったらもっと楽しい」ことを増やしていくことで自信に繋げ自己効力感を育みます。
運動・感覚
運動教室や戸外活動を通じて体力増進に繋げ、手指訓練や季節感を養うと同時に友達と協力して行う制作で「協調性」を養います。
事業所外での社会的な場面(高齢者との交流)での共生活動(調理・盛り付け・配膳・掃除)を通じて適応能力向上のための支援を行います。
認知・行動
興味関心に沿って様々な提案を行い、自己選択・自己決定ができるプロセスを経験できるようにします。
慣れない作業に不安はあるが、毎日行う事で少しずつ自信に繋げていき、与えられた役割を担うことの大切さを経験できるように促していきます。
言語・コミュニケーション
子どもたちが発信するサインに大人が呼応することで疎通性が高まり「伝わった」という実感を積み重ねられるようにしていきます。
言語に限らず、表情や仕草、全身運動、子供会議など様々な手段を通じて、伝える力・受け取る力を身に着け、自らの思いに自信を持って発信できる場面づくりを行います。
人間関係・社会性
一人遊びから協同遊びの支援としてコミュニケーションが必要となる環境・活動を通して徐々に社会性の発達を支援していきます。
日常生活の中から個々の子どもたちの可能性と課題を見つけ、様々なレクリエーションを行うなかで余暇時間の充実や集団や社会でのルールを学ぶ機会を提供していきます。
家族支援
- 送迎時や電話、面談などを通じてやり取りする機会を設けます。
- 発達状況に関する相談援助・子育てや特性に関する情報提供・兄弟への相談援助
- 保護者同士の交流の機会
- 仕事や所用などでの預かり希望の対応
移行支援
- 移行先の学校や就労支援機関についての情報を提供し、選択肢を広げます。
- 保護者に対しても移行に関する情報や支援を提供し共に考える場を設けます
- 児童館や地域の行事等へ積極的に参加し、地域社会との繋がりに向けた取り組みを行います。
地域支援・地域連携
- 学校、併用先、相談支援事業所などと情報共有を行い、密な連携を図る。
- 高齢者との共生活動で共同学習の場の提供をすることで互いに知識の共有を図る。
職員の質の向上
- 社内外研修への参加をし、得た情報・知識を毎月の職員会議で報告します。
- 毎日のミーティングで児童やレクリエーションの振り返りを行い、支援の中での気付きや変化を職員間で共有し児童との関わり方や散り組み方の意見交換を行います。
主な行事等
【放課後等デイサービスレク】
- 制作
- お誕生日会
- 戸外活動
- 外出レク
- クッキング
- ビジョントレーニング
- SST
- 仕事について学ぶ・茶話会
【高齢者との関り】
- 高齢者のバイタルチェック
- 食事の盛り付け、配膳
- 高齢者が過ごすスペースの清掃活動
- 絵本読み聞かせ
【共生レク】
- お花見ピクニック
- 七夕まつり
- 敬老会
- 共同避難訓練(火災・津波)
- 豆まき会
- ひな祭り会
- 畑作業
【地域交流】
- 町内会行事への参加(夏祭り・ひな祭り会)
- 文化祭への作品出品及び参加